キッチンタイマーをテーマにした
お話の2回目です。
こころの病気を抱える本人と暮らす家族は大変…
当事者の家族である私にはよく理解できます。
そこで、
是非とも家族に持って欲しい視点をお伝えします。
今回の話の内容は、私たちの実体験をもとにしています。
皆さまの参考になれば幸いです。
それではどうぞ。
問題点:2回目の入院から退院した直後の彼女…大丈夫?
・以前のようにバリバリと動けない
・テンションも少し低め
・活動的になれない
これが当時の彼女の状態でした。
さすがに私も不安になりました。
もし、
このまま何も対処しないと…
・生活にメリハリが無くなる
・生活のリズムが乱れてくる
・体調の悪化につながる
こんな…
未来予想図2が私の脳裏をよぎりました。
解決策:キッチンタイマーを使った理由に注目!!
無理をしない程度の生活管理は必要という結論に至った私たち。
いろいろと試行錯誤をした果てに
たどり着いた答え…
それが
キッチンタイマーでした。
理由は、
料理を作っている時に、
キッチンタイマーを上手く使いこなせていたからです。
その姿を見て
「これは使える!!」と私は直感しました。
ただし、
キッチンタイマーを彼女に手渡して
「これ(キッチンタイマー)持って、あとは自分で頑張って」と
いうことはしませんでした。
こころの病気を抱えている人は、
持続力が続かないことが多いです。
無理に続けさせようとすると、
ストレスとなり、
体調を崩すことにもつながりやすく、
逆効果になりますね。
一人では、どう考えても無理がある。
そこで、私が家にいる時に
「二人」で行うことにしました。
つまり、共同作業にしたのです。
具体例:どんな風にして、キッチンタイマーを使ったの?

起床
朝はいつも私が先に起きます。
しばらくしてから、彼女に声をかけて
「朝やで。起きよう!」と起こそうとするのですが…
「あと5分…あと10分」と
言ってなかなか起きません。
そうなのです。
彼女は朝起きるのが苦手です。
そこで、
朝私が彼女を起こす時に
「キッチンタイマーであと何分で起きる?」と
彼女自身にセットしてもらいます。
お出かけの準備
これも「起床」と同じ要領です。
彼女に「キッチンタイマーであと何分でお出かけの準備を始める?」と
彼女自身にセットしてもらいます。
教訓:当事者とその家族が幸せに暮らすための視点
今回の教訓は二つです。
普段つかい慣れているもの、好きなものを上手く活用する
自分がやりたくない事を行うために、
新しいことを覚えるのって、すごく抵抗感がありますよね。
だから、
普段からできていることを
上手く利用します。
少しでも抵抗感を小さくします。
今回の場合は、
キッチンタイマーです。
大好きな料理で使っているキッチンタイマーは、
彼女にとって愛着あるグッズです。
そのグッズを今回は上手く活用しました。
家族も協力する
家族の協力は、今回に限ったことではありません。
常に念頭に置いておくべきことですね。
そして、
覚えてほしい注意点が二つあります。
・上手くいかなくても怒らない。
・上手くいった時は、思いっきり喜ぶ。
今でも、
私たちは心がけています。
まとめ+おまけ
いかがでしたか。
こころの病気を抱えると…
当事者とその家族は何かと大変です。
それでも、実生活の中に、
幸せに生きるヒントはたくさん隠されています。
今回の話が少しでも参考になれば幸いです。
最後に、
オススメのキッチンタイマーを
紹介しますね。
かわいい
「イチゴのキッチンタイマー」です♪
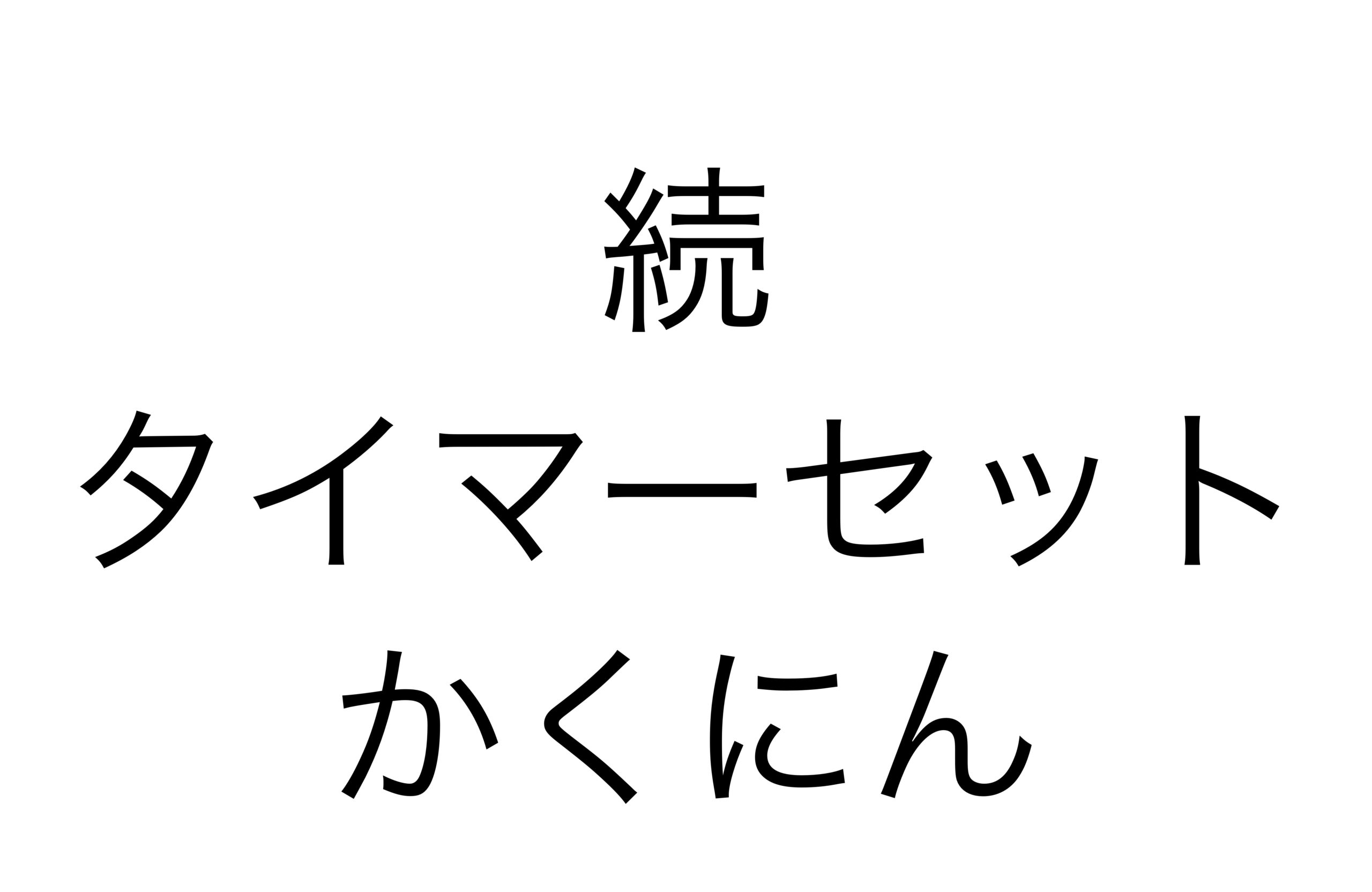
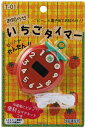
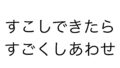
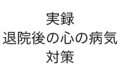
コメント