こころの病気を抱える彼女と
介護士の私との生活から生まれた
幸せの法則
今回は「だいじょぶ」
という言葉についてお話します。
そして今回の話の内容は
介護で働く人たちにも役立つ話となっています。
どうか最後まで
お付き合い下さい。
以前の私たち
彼女はこころの病気を抱えています。
すると彼女も私も
すごく不安になるときがあります。
- いつまで、この二人の生活を続けられるのだろう?
- 彼女の調子が悪くなって入院にならないだろうか?
- 今の介護の仕事…いつまで続けられる?
明確な理由や根拠が
あるわけではありません。
それでも漠然とした不安が
湧き出てくることがあります。
以前の私たちは…
無理にポジティブなことを考えて、
不安を打ち消そうと躍起になっていました。
でも逆効果。
余計に疲れてしまいます。
喧嘩になってしまうことも
度々ありました。
最近の私たち
最近になって
分かってきたことがあります。
それは
「こころの病気を抱えている人の場合、無理にポジティブになろうとするのは禁物」
ということです。
少しネガティヴなくらいで
ちょうどよい気がします。
その結果、もしも不安になった時に、
掛け合う言葉が最近の私たちにはあります。
「だいじょうぶ」です。
この言葉に込められた想いは…
不安な気持ちを肯定も否定もせず、
そのままを受け入れること。
↑
ここポイントですね。
まだまだ、
上手く使えていないこともあります。
ちょっと
落ち込んでしまうこともあります。
それでも
だいじょうぶ
だいじょうぶ
だいじょうぶ
…と繰り返し使います。
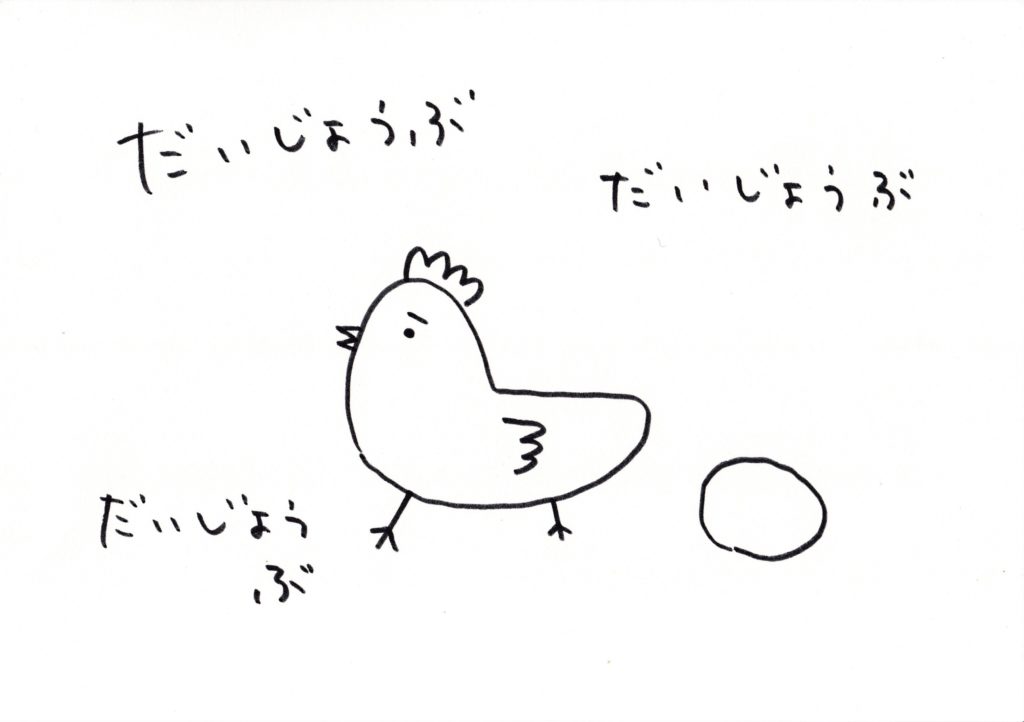
以前の私の介護
この「だいじょうぶ」という言葉は介護で働く人たちにも有効です。
私たちが普段接している利用者さんは、多くの場合、心身の状態が改善することはありません。
最初に誤解のないように説明しておきますが、
- オムツから紙パンツになった
- 嚥下機能が回復して経口摂取が復活した
- 歩行できるようにんった
などの個別の身体機能の改善はあります。
さらに、私たち介護士も
自分のたちの知識と経験を用いて
最大限のサポートをしなければなりません。
しかし、大きな視点で見ると
心身の機能はゆっくりと低下していきます。
これは自然の法則です。
この法則に逆らうことはできません。
しかし、
その状態をありのまま受け入れない人がいます。
その結果、
- 本人が嫌がっているのに、従来のリハビリにこだわり続けて、誤嚥や皮下出血などを引き起こす。
- 悲観的になって、本人への興味を無くしてしまい、身体機能のレベル低下が急速に進む。
このように本人や周りの人たちに、
よくない結果を招いてしまうこともあります。
最近の私の介護
こんな時、
「だいじょうぶ」という言葉とその意味を
知っていたらどうでしょうか?
だいじょうぶ
だいじょうぶ
だいじょうぶ
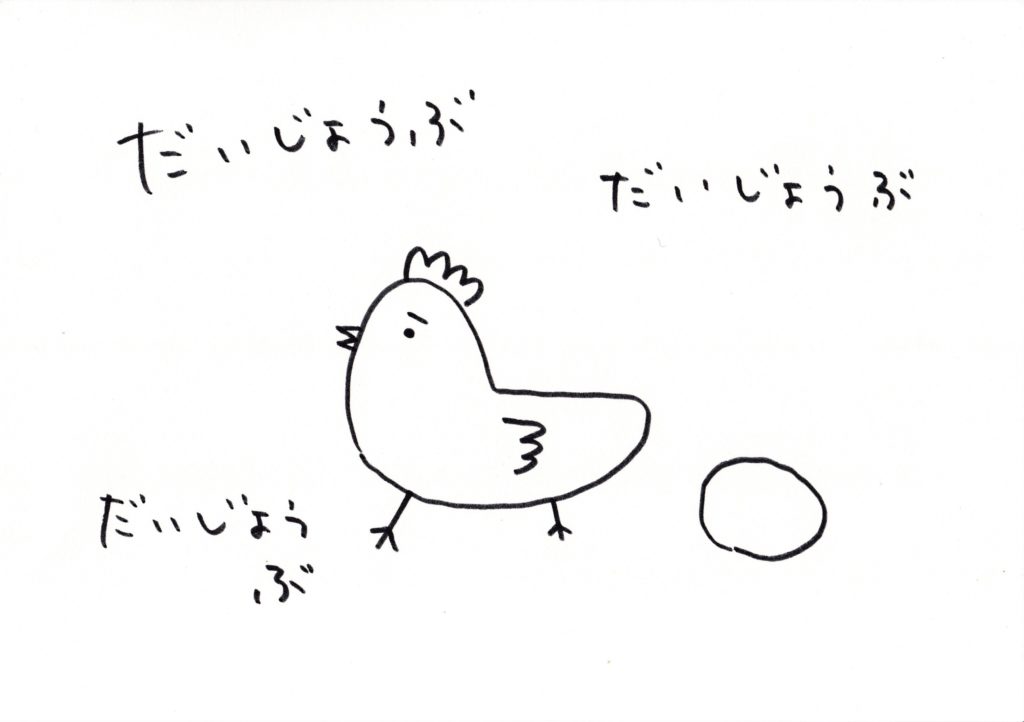
現在の利用者さんの状態を
ありのまま受け入れます。
その状態が、
「良い悪い」「悪化改善」などの判断をしません。
ただありのまま受け入れます。
すると、
ネガティヴな感情に引っ張られることが減ります。
そして、今の状態の利用者さんにできることを
考えることができます。
結構使えます。
騙されたと思って
一度実践してみては?
まとめ
いかがでしたか。
「だいじょうぶ」という言葉を使い、
その言葉の意味を知ると、
介護での仕事で受ける辛い想いが
少し減るかもしれません。
私は実際にこの言葉とその意味を知ってから、
介護の仕事が少し楽になりました。
よかったら、
一度お試しください。
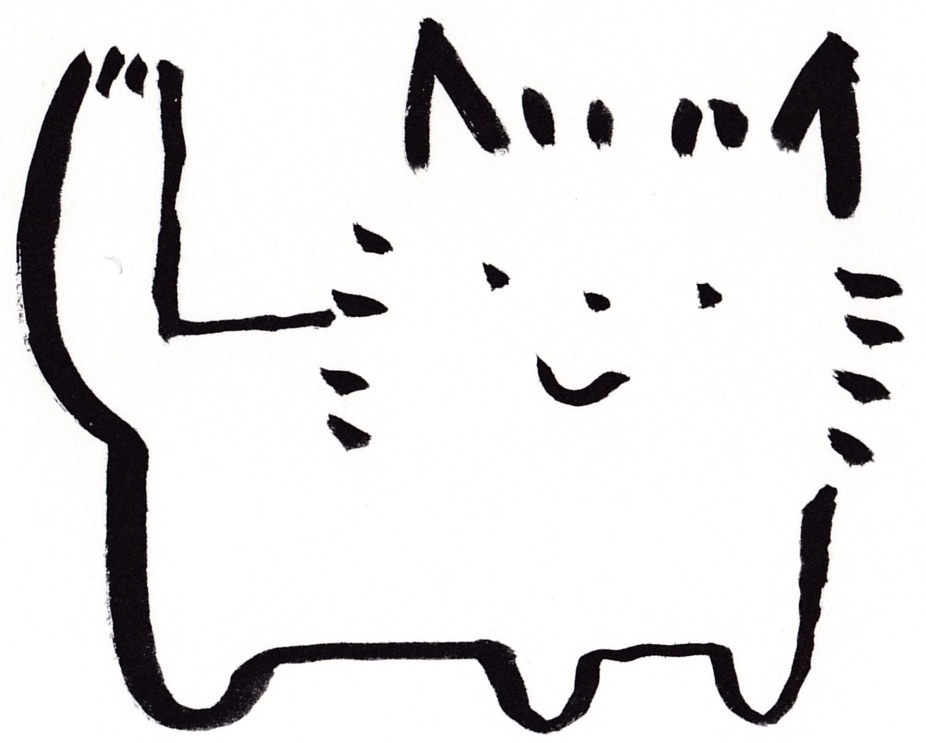
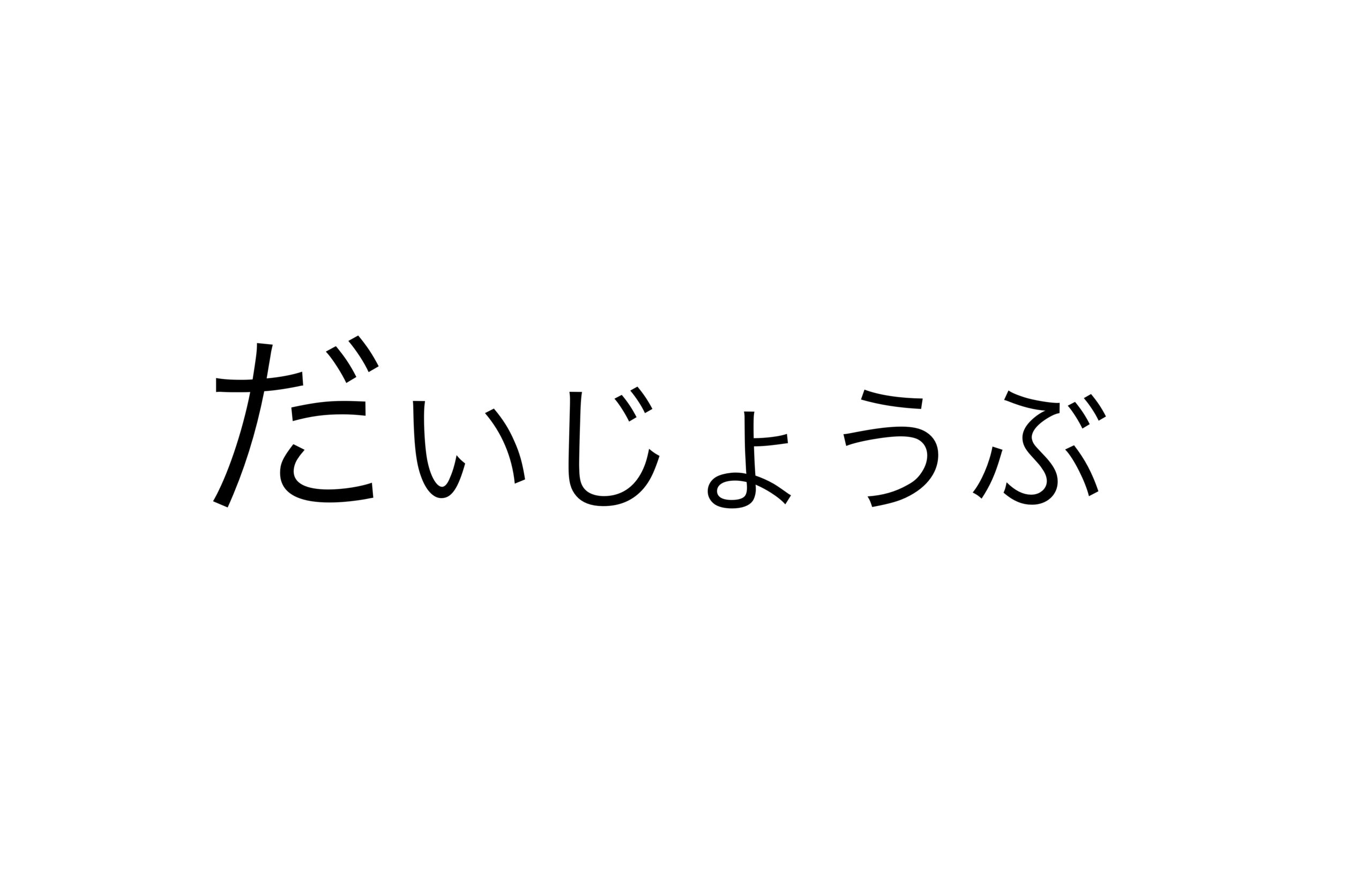

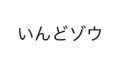
コメント